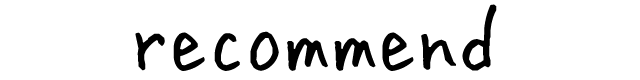日本の食糧自給率を考える:未来への選択
2024.12.23食べもの

日本の食糧自給率は、カロリーベースでわずか39%(2023年度)と、先進国の中で極めて低い水準にあります。これは、国内で消費される食料のうち約6割が輸入に依存していることを意味します。さらに、農業に必要な肥料や種の多くが輸入品であるため、「実質的な自給率」は約9%に過ぎないとの指摘もあります。この状況は、自然災害や地政学的リスクによる食料供給の途絶という深刻な問題を孕んでいます。では、この問題に対して、どのような対策が取られているのでしょうか。また、私たちには何ができるのでしょうか。
農家や政府の取り組み
農協や農家は、食糧自給率の向上に向けた多様な取り組みを進めています。その一つが、地産地消の推進です。地元で生産された農作物を地元で消費することにより、輸送コストや環境負荷を削減すると同時に、地域経済を活性化させる狙いがあります。また、農家の高齢化や後継者不足といった課題に対応するため、農業に参入する若者を支援する制度や、ICT(情報通信技術)を活用したスマート農業の導入も進んでいます。スマート農業では、ドローンやAIを使った効率的な農作業が実現し、人手不足を補うだけでなく、収穫量の安定化にも寄与しています。
政府もまた食糧自給率の改善を目指して様々な政策を実施しています。その代表的なものが、「食料・農業・農村基本計画」に基づく施策です。この計画では、耕作放棄地の再活用や、中山間地における農業の振興が重要視されています。また、国内の農業を守るために、輸入品に対する関税や補助金の提供を行い、国産農産物の価格競争力を高める努力も続けられています。さらに、食育の推進を通じて、国民一人ひとりが日本の農業に関心を持ち、国産品を選ぶ意識を育むことも狙いの一つです。


食糧自給率向上のために私たちにできること
このような背景の中で、私たち個人ができることも少なくありません。まずは、国産品を選ぶことが挙げられます。スーパーでの買い物の際に地元産や国産の食品を選ぶことで、国内農業を支援し、食糧自給率向上に寄与することができます。また、フードロスを減らす努力も重要です。日本では年間600万トン以上の食品が廃棄されており、これを削減することで、限られた資源を有効活用することができます。
さらに、家庭菜園やベランダでの野菜栽培といった小さな取り組みも、食糧自給率の改善に繋がる一助となります。自分で育てた野菜を食べることで、食べ物に対する感謝の気持ちが深まり、持続可能な食生活への意識が高まります。また、地元の農業イベントや直売所を訪れ、生産者と直接交流することで、農業の現状を学び、地域の農業を支援することができます。
日本の食糧自給率の低下は、農業従事者や政府だけで解決できる問題ではありません。私たち一人ひとりが、自分たちの食生活を見直し、日々の行動に変化を加えることが必要です。輸入に依存することのリスクを理解し、地元産や国産の食材を積極的に選ぶことで、国内農業の持続可能性を支えることができます。
未来の子どもたちが安心して暮らせる社会を築くために、私たち全員が「食」を真剣に考え、行動する時が来ています。その一歩として、まずは日々の食卓を見直し、地産地消やフードロス削減といった小さな努力から始めてみませんか。


− writer