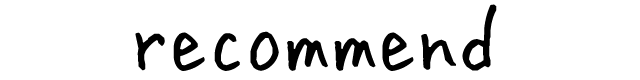乾物とおせち:日本の伝統食材と祝いの心
2024.12.16食べもの

乾物は、日本の食文化に深く根付いた保存食品であり、その長所は栄養価の高さと保存性にあります。乾物とは、食品を乾燥させて水分を抜いたもので、保存が効きやすく、食材本来の旨味が凝縮されています。この伝統食材は、古くから人々の暮らしを支え、四季折々の行事や祝祭の場面で重要な役割を果たしてきました。特におせち料理においては、乾物が欠かせない存在です。
おせちに使われる乾物
おせち料理は、正月を祝うための特別な料理であり、年神様への供物としての側面を持つ伝統的な行事食です。その起源は平安時代にさかのぼり、季節の節目に神々への感謝を捧げる「節供」の一環として発展しました。乾物が多用される理由のひとつは、保存性の高さです。新年を迎える前に準備を整え、大晦日から数日間は台所仕事を控えるという風習に適した食材として、乾物が重宝されてきました。
【昆布】
昆布は、日本の乾物を代表する食材のひとつで、出汁の基盤としても使われます。おせち料理では「結び昆布」や「昆布巻き」として用いられ、「喜ぶ」に通じる縁起の良い食材です。また、昆布は長寿を象徴し、家族の健康と幸せを願う意味が込められています。
【干し椎茸】
干し椎茸は旨味成分が豊富で、煮物に使われることが多い乾物です。おせちでは煮しめの材料として欠かせません。その独特の風味とコクが料理全体を引き立てると同時に、形状が傘を広げるような見た目から「繁栄」や「成長」を願う象徴とされています。
【かんぴょう】
かんぴょうは細長い形状から「長寿」を連想させるため、おせちで多用されます。昆布巻きや煮物の飾りに使われることが一般的で、食材を束ねる役割も果たし、「結びつき」の願いが込められています。
【高野豆腐】
豆腐を凍結乾燥させた高野豆腐は、保存性と栄養価が高い食品です。おせちでは「含め煮」として使われ、吸収した出汁の旨味を楽しむことができます。高野豆腐は、平和と豊かさを象徴すると言われています。
【田作り/ごまめ】
「田作り」(主に東日本での呼称)という名前には、豊作を祈る意味があり、かつて田畑の肥料として使われた歴史に由来します。甘辛く味付けされた田作りは、お正月の食卓を彩る一品です。関西では「ごまめ」と呼ばれることが多く、諸説ありますが、「五万米」と表記されることもあり五穀豊穣やイワシは非常に多くの卵を産むことから、子孫繁栄の象徴を意味するということなどに由来しているようです。


乾物の意義と現代への応用
乾物は単なる保存食ではなく、日本人の知恵と工夫の結晶であり、祝祭や日常の食事に深い意義を持っています。おせち料理における乾物の使用は、長い歴史と文化的な意味合いを伝える役割を果たしています。その中には「家族の健康」「長寿」「豊作」「繁栄」といった願いが込められ、それらは現代においても色あせることのない普遍的な価値観です。
近年では、乾物が持つ栄養価や保存性が再評価され、健康志向の高まりとともに注目を集めています。新しい料理法や海外の食文化との融合を試みる動きも見られ、乾物はますます多様な形で活用されています。それでもなお、おせち料理の伝統の中で乾物が占める役割は変わらず、世代を超えて受け継がれる日本の誇るべき食文化の一端を担っています。
おせち料理を通じて乾物に込められた日本の心を再確認し、その美味しさや魅力を未来につないでいきたいものです。


− information

みわび
「みわび」は、「にっぽんのおいしいをここから」をテーマに日本アクセスがお届けする乾物シリーズです。https://accessbrand.nippon-access.co.jp/miwabi-category/miwabi-a/
− writer