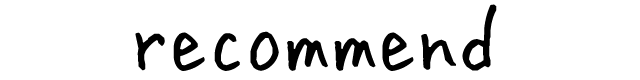住まい方・暮らし方の新しい流れ
2021.07.19暮らし

人も企業も
2010年代から「移住」や「田舎暮らし」という文字がメディア上でにぎやかになってきた。都会の生活から田舎の生活へ。その呼び水となったのが、地方自治体の移住者支援制度だ。過疎化が進む自治体が移住者に対して補助金を出したり、家を安く提供したりと、様々な工夫を凝らして田舎に人を呼び込むことに力を注いできた。だが、一番の問題点は移住先で満足できる仕事が見つかるのかということで、結果的に移住が可能なのは農業に興味のある人や芸術系の創作者、もしくは定年退職後の夫婦など、少し特殊な事情の人々に限定されることが多かった。そのため、メディアの喧騒とは裏腹に、自治体が狙ったほど移住が進まない現実があった。
ところが約1年半前、新型コロナウイルスの流行が始まり、その様子が一変した。大方の企業が、リモートワークやオンラインミーティングを進めるようになり、働き方が変わったのだ。会議はオンライン会議ツールで十分であり、リモートワークで家にいても、可能な仕事はこなせるという事もわかった。さらに、多くの人がわかったことは、今まで、いかに場所と時間に制約された生活をしていたかということだ。当たり前のことであり、誰しもわかっていたことだが、新型コロナによって、その事実を改めて眼前に突き付けられた。その気付きは働き手ばかりでなく、企業側にとっても大きなことだった。
あるドキュメンタリー番組で見たのだが、大手の人材派遣会社は、営業以外の部門を淡路島に移した。夫婦で同会社に勤めるAさんも、淡路島に親子3人で移住することになった。当初、不安はあったが、1年が経過した今は、とても充実しているという。移動手段は車だ。会社まで10分の場所に、会社から斡旋を受けた2LDKの戸建て住宅に住んでいる。夫婦共働きだが、会社は定時に終わり、保育園も完備されているから何の心配もない。なにより、朝夕に眺める瀬戸内海の美しい景色や田舎のゆっくりとしたリズムに癒されると話すAさん。週末の楽しみ方も変わったという。この企業以外にもレコード会社から芸能プロダクションまで、この1年で田舎に移転したり、サテライトオフィスを設ける企業が後を絶たない。会社にとっては経済的なメリットを享受できると共に、従業員への福利厚生の充実や精神衛生上の保全にも役に立っているという。


プチ移住という選択
「移住」への流れは、企業だけにとどまった話ではない。この機に個人で移住する人も増えている。最初に移住を始めたのは、オンライン会議やリモートワークが社会通念として許容されるようになった恩恵を直接的に受けることができるIT系のプログラマーや様々なクリエイター達だ。思い切って北海道や沖縄に行く人もいるという。東京在住の人にとっては、山梨や伊豆、那須なども人気だと言う。
だが、一般会社員は、なかなか移住までは難しいと思っていた私を、とても驚かせた事実がある。それは、2021年4月の東京からの転出人口が2万5千人以上になったこと。そして、その大半の転入先が千葉、埼玉、神奈川だったことだ。しかも、東京に隣接した場所ではないという。つまり、「プチ移住」なのだ。「通勤時間が、今までの倍になっても、週に2日はリモートワークになるので、我慢できる。」そんな人が増えているのだと言う。手狭な都内のマンションからプチ田舎の広い戸建てに移る。家に居る時間が長くなった分、その暮らしを豊かにしたいと思うのは当たり前である。
神奈川でいえば、厚木の奥や、小田原周辺。千葉は木更津や九十九里など。自然も満喫できて、暮らしに必要な施設も問題ない。都内なら家を建てるための高い障害となる土地代も、このあたりなら安い。昨年はコロナ過にもかかわらず、住宅メーカーは郊外地で販売を伸ばした会社が多かった。けん引役は、おそらく彼らプチ移住者たちだろう。その証拠に、設計段階で「リモートワークスペース」という言葉が、施主の口から発せられることが多かったと、住宅メーカーの営業マンが教えてくれた。
法律やルールを決めることによって「働き方改革」などと声高に叫んでも、さほどのムーブメントは起こらないのが常だが、眼前の非日常状態は、あっという間に、社会通念や我々の常識を変えてムーブメントへと覚醒する。この住まい方や暮らし方は、例えコロナ騒ぎが収束しても、元に戻ることは無いのではないかと思う。


− writer